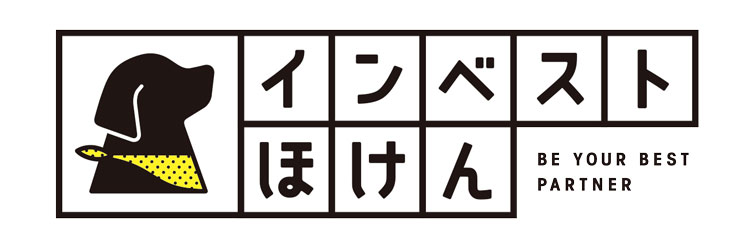蚊取り線香の容器が豚の理由!蚊取り線香はなぜ左巻き?
毎日暑い日が続いております。みなさま体調はいかがですか?
夏と言えば色々ありますが(海・スイカ・アイス・焼肉などなど)
今回は蚊取り線香のお話です。
蚊取り線香の容器が、なぜ豚の格好(かっこう)をしているのかについては、諸説あるようですが正式には“蚊遣器(かやりき)”と言います。
基本的には、蚊取り線香を安定して燃焼させ、且つ肺の飛散を防いで、後片付けを簡単にするための道具です。なぜ豚の格好をしているかについては色々で、一つには蚊取り線香が発明される以前の江戸時代末期の東京新宿区の武家屋敷跡から、杉の葉などをいぶして蚊を追い払った「蚊取り豚」が出土したから。二つ目が昭和20年代以降の常滑発詳説で、養豚業者が豚の蚊よけのために、最初は円筒形の「土管」の中に蚊取り線香を入れていましたが
土管は口が広すぎて、煙がすぐ拡散してしまうので、少しづつ片側を縮めていくうちに形が、豚に似てきましたそこで、「せっかくだから」と、豚の形の「蚊遣器」にして、常滑焼のお土産にしたところ、大ヒットして全国に広まったという説です。
じっさいどうなんでしょうかね。^^
中に入れる蚊取り線香ですが
初期型の蚊取り線香は、なんと手巻きで製造していたそうです。
この初期型をよく見ると今とは逆の「右巻き」だったのです。昭和中期頃から機械による打ち抜き方式に変わって行きましたが、その際、右巻きから左巻きに変更されました。
理由は、この頃になると、各社から蚊取り線香が販売されており、其の為少しでも他社との差別化を図りたいという意図で、左巻きにしたとのことです。(笑)
販売戦略ということです。
普段気にしていない事や物でも諸説あったり、時代背景の影響だったり楽しいですね。
札幌手稲店
五十嵐